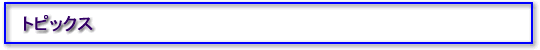今年9月14日に国税庁がホームページに掲載した『平成19年7月4日付 資産課税課情報第14号 「相続税法基本通達」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)』の中にミスリードがありました。
ミスリードが見つかったのは、同情報の【相続税法第9条の2 ((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係】内の「9の2-1 受益者として権利を現に有する者」の説明文にある【相続税及び贈与税関係の改正の概要】「3 受益者等が存しない信託に係る課税の特例」の(2)のイ及びロの文節です。
これまで、「イ、受益者等の存しない信託の効力が生じた場合」として「・・・、当該信託の受益者等となる者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(委託者の死亡に基因して信託の効力が生ずる場合は遺贈)により取得したものとみなして贈与税(遺贈の場合は相続税)を課税することとされた(法9の4(1))」としていました。これについて国税庁は、下線部が間違っていて「当該信託の受託者は」が正しいとしています。また、「ロ、受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなった場合」についても「・・・、当該信託の次に受益者等となる者は、当該前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(前の受益者等の死亡に基因して受益者等が存しないこととなる場合は遺贈)により取得したものとみなして贈与税(遺贈の場合は相続税)を課税することとされた(法9の4(2))」としていましたが、下線部について国税庁では「当該信託の受託者は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等から」が正しかったとして訂正しています。
このほど、国税庁がe-Taxホームページ(国税の電子申告専用サイト)に掲載している「よくある質問(Q&A)」コーナーに、平成20年1月から適用できることになっている「電子証明書等特別控除」(電子申告控除)や「第三者作成書類の確定申告書への添付省略」などについて、納税者から問い合わせの多いものを追加しました。
今回、同Q&Aに追加した項目の中でも注目されているのは、電子申告控除に関するものです。電子申告控除は、電子政府の推進のため、国や地方自治体にオンライン申請などを行う際に必要な住民基本台帳カードと公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダライタなどの取得を税制面で支援するために平成19年度税制改正で創設されたものです。
具体的には、平成19年分か、または、平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名と電子証明書を付して、提出期間内にe-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円の控除が受けられるというものです。
追加されたQ&Aの項目で、最も注意しなければならないのは、税理士に電子申告を任せた場合にも同控除が適用できるかという質問です。税理士による代理送信により申告書を提出する場合に、税理士・納税者本人双方の電子署名及び電子証明書を付して行われるときは、本税額控除の適用を受けることができますが、税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは、納税者本人の電子署名及び電子証明書が付されていないことから、本税額控除の適用を受けることはできない―としていますので、この点は必ず踏まえておく必要があります。
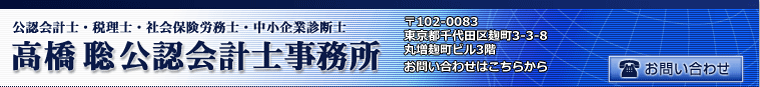
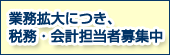

 当事務所は上場ドットコム
当事務所は上場ドットコム